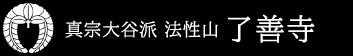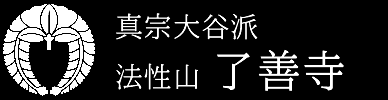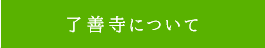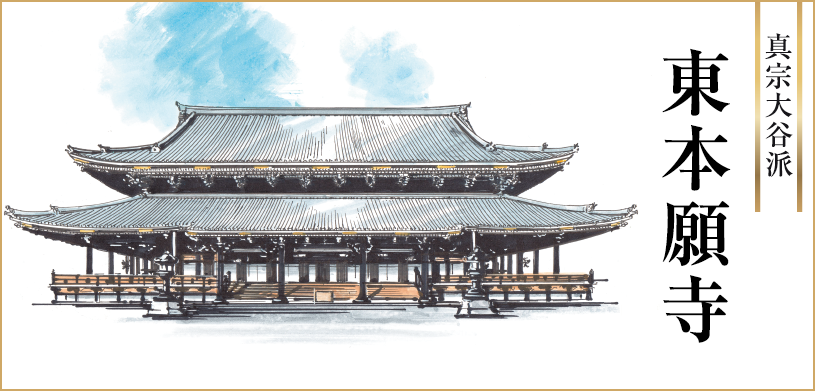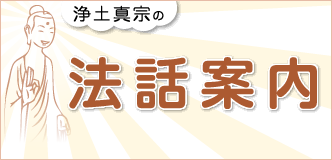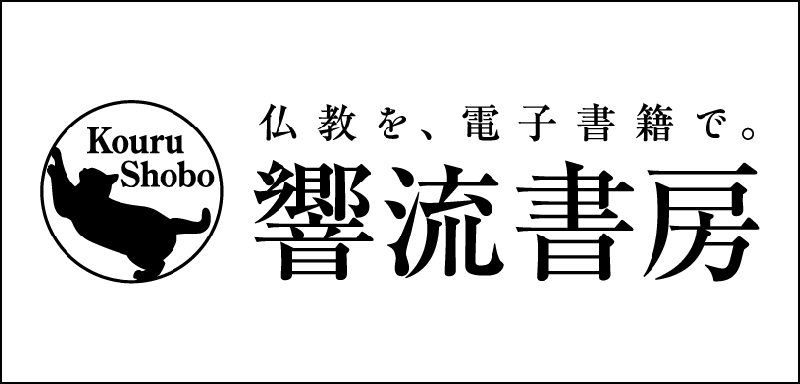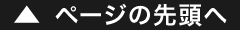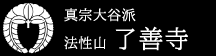「浄土がこちらへくる」
2025.04.07

「浄土は本願の世界ですから、浄土は本願に乗じて、本願に乗託して生死の世界にくる。それを如来の回向という。浄土へ往くのではなくて浄土がこちらへくる。それを本願成就という。そういう言葉はどこに書いてあるか。それは書いてない。けれども、書いてあることばかり言って書いていないことは言わんというなら、それはつまらんですよ。書いていないことも言えるようにならなければ―。書いてないことを言ってもいいということではないですが、書いてあることしか言われないというのでは―」(曽我量深師講義録上巻『教行信証大綱』44頁)
「浄土がこちらへくる」という一言が目に飛び込んできたので、思わず抜き書きしました。「昭和37年4月24日」の講義録ですので、師は満87歳を迎える年です。「大信心はすなわちこれ、長生不死の神方」(聖典①211頁)、信心は他力ですから、信心に老化はないのです。いつも若くフレッシュです。
「何でも言っていいと言っておるわけではありません。言いたいことがあれば何でも言っていいということがあります」。
言葉が躍動しています。教理の解説など、とうに超えています。
曽我先生と暁烏先生は、終生深い交わりがありました。暁烏先生は、清沢先生の直弟子として、一目置いておられたのが曽我先生です。お二人のことは、本山から刊行されている『曽我量深集』や『曽我量深講義集』等に記されていますが、2歳年下の暁烏先生は大腸がんを縁として、昭和29年8月27日にご西帰されます。
明達寺(暁烏敏師の自坊・石川県白山市)には数多くご出講されていますが、 暁烏師の年忌法要にも、毎回曽我先生が出講されています。併せて、金子先生や藤原鉄乗先生、松原祐善先生も出講されています。
当時、マイク係を仰せつかっていた松田章一先生曰く、「マイクの調子が悪くなった時に備えて、演壇の脇でかがんで待機していたんです。法話の熱が上がり、満堂の聴衆が聞き入っていると、ポコ!・ポコ!・ポコ!・・と妙な音がし始めたんです。不規則ですが、ポコポコという音が続くのです。マイクかな、スピーカーの不具合かな・・法話中なので弱ったなぁ・・と耳を澄ますと、 ポコ!の音源は何と演壇でした。立ち上がって獅子吼される曽我先生が興奮して演壇の内側を足で蹴っているんです。ポコポコは、演壇を蹴る音だったんですよ。法話はみんな忘れましたが、あのポコポコだけは、ハッキリと覚えています。曽我量深と聞くと、あのポコポコの・・という具合に連想するのです」。
ポコポコだけが耳の底に残ったとは、何とも有難いですねぇ・・南無阿弥陀仏。