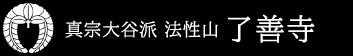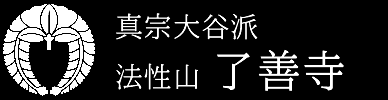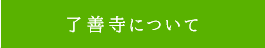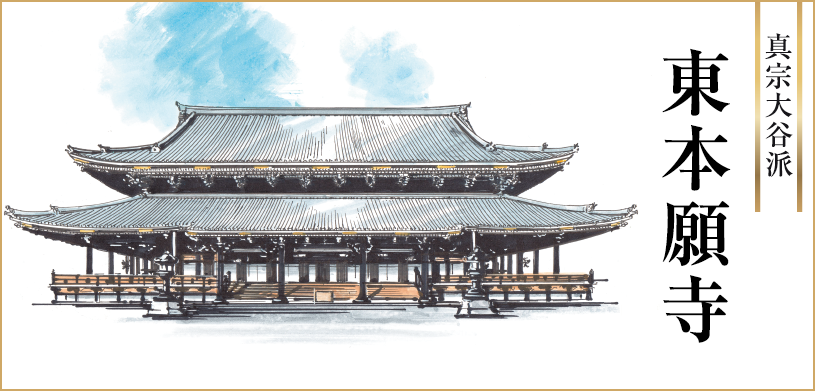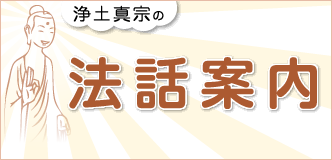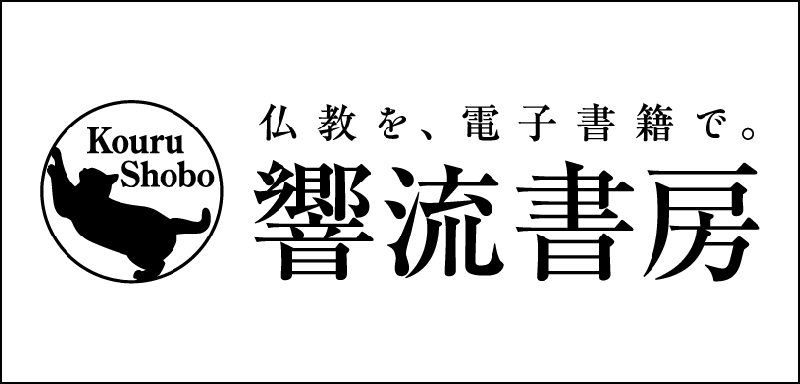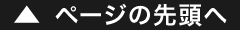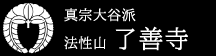人並外れた仏法
2025.09.30
池田勇諦先生の法話録『仏教の救い④―アジャセの帰仏に学ぶ』(全5巻・北國新聞社・2017年)を再読しています。ご法話でも聞いた師の祖母様の「口癖」に驚かされました。
「人並みに仏法を聞いとったら、人並みの仏法しか分からん。人並み外れて聞かんことには、人並み外れた仏法は分からんぞ」(前掲書70頁)
池田勇少年の求道心を生みだした善知識が、この祖母様でした。妙好人森ひなを生んだ、石川県小松市瀬領町の人です。桑名に転居されてからは、晩年盲目になられた祖母様は、勇少年に手を引かれて、毎日桑名別院に参詣していました。当時の別院は、毎日法話があったのです。
「人並みの仏法」とは、実は「人間の教え」にすぎず、「仏法」ではないということでしょう。仏法は経典の題名にあるとおり、「過度人道」です。
仏法は人間の誠意を至上価値とするヒューマニズム(人道)や善悪のモノサシに立った理想論、あるいは倫理道徳ではないのです。
ですが「人並みの仏法」は、私の価値観と地続きですから、わかりやすく聞きやすく耳になじむのです。またそのように聞きかえてしまうのです。
蓮如上人のご法話のあと、感動した6名が「今日のご法話を忘れては勿体ないから」と確かめ合いをされました。一人ひとり感想を述べたところ、6人6様だったそうです。響くところは異なりましょうし、違う感想を聞くことで自らの受けとめが問い返されることもあります。
ところが、6人の内4人までもが法話の趣旨を聞き違えていたというのです。
この逸話を伝える『蓮如上人御一代記聞書』第48条 は「ききまどいあるものなり」(『聖典』第一版864頁・第二版1037頁)と結ばれています。
一座の法話を「あまりにありがたき御掟ども」(同上)と感じていた4名は、いったい何に感動されていたのでしょうか。自分にわかるように聞きかえてしまっていたのでしょう。私も身に覚えがあることです。
あるとき、池田先生に仏法聴聞についてお尋ねしたら、「正しく聞く、ということが大切だ」と。当たり前のことを言われるな、と思っていましたが、今にして思えば「百々海は正しく聞いとらんぞ」ということでしょう。
「ききまどい」とは、聞くことで惑いを深める―との鋭い一言です。「ききまどい」を「ききまどい」と知らせるはたらきこそが、仏法なのでした。南無阿弥陀仏