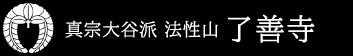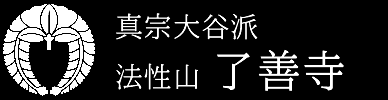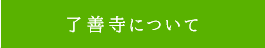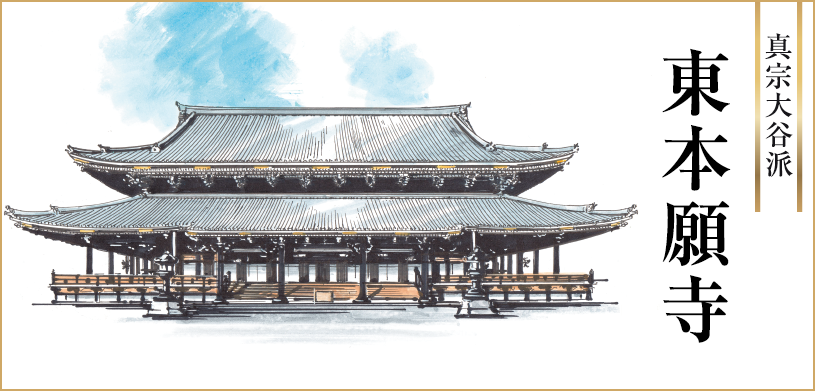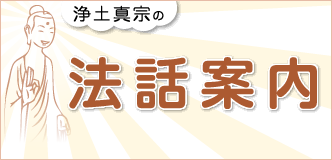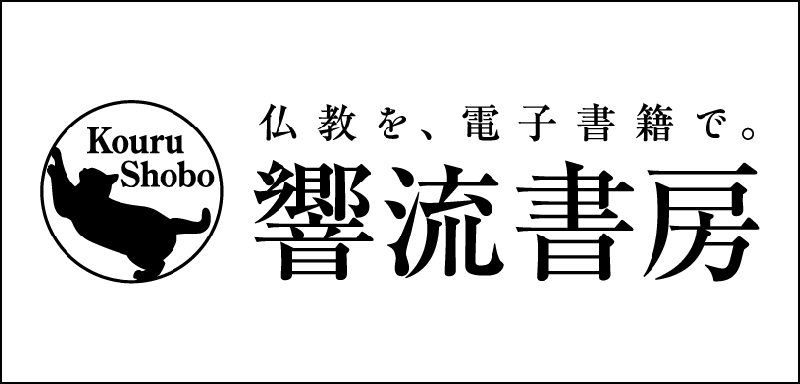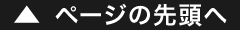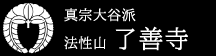祖師親鸞聖人のご命日を前に
2025.11.26
金子大榮師の『観無量寿経講話』(『金子大榮選集』第19巻所収)を再読している。奥付は昭和31(1956)年4月10日発行となっており、序文も同年3月15日付であるが、後記は昭和12(1937)年1月16日付、初刊行の際に記したものである。後記だから、当然ながら講述されたのは昭和12年以前、現在から88年以上前である。
が全く古びない。それは金子師ご自身もご自身の選集に収載されたのだから、ご自身に響いていたに違いないことは容易に拝察できる。法を説いている限りにおいて、時代の制約は超える。
文字を超えた本願のまことを文字であらわしているのだが、読んでいる私がすっかり読みぬかれているとしか言えない、主体の転換を起こす力がある。以前読んだ時とは、まったく感じが違うのも興味深い。
とりわけ、次の一節は、親鸞聖人のご命日を目前にして潮騒の如くに轟いてくる。
「親鸞が学問の結論として念仏するのでなく、親鸞の長い間の人間生活、人生体験というものが親鸞をして念仏せしめるのである」 (同書26頁)
上掲の「親鸞」を悲劇の王妃「韋提希」(イダイケ)に置き換えても、およそ生けるものすべてに置き換えても通じる。仏法は人生上の問題を解決する為の処世術でなく、解決絶無の人生を念仏申す縁に転じてくださるのである。
年5月 暁烏師13回忌法要 法話・金子大榮師(横山定男氏撮影).jpg)
1966(昭和41)年5月 暁烏敏師13回忌法要 明達寺本堂にて
演壇左手 眼鏡・坊主頭=西村見暁師
撮影:横山定男氏 ※無断転載厳禁
『歎異抄』第8条に「念仏は行者のために、非行非善なり」とあるとおり、念仏とは、処世術として、救済手段として、私が利用する行には非ざるのである。念仏はいつ、どこで、誰が、どんな心持ちで称えようと、「ひとえに他力」である。「ひとえに他力」なればこそ、私が思い描く「私+念仏=救済」という青写真を瞬時に粉砕してくださるのである。
「祖師も師も父も称えし念仏をわれも称えて南無阿弥陀仏」(林暁宇師)。
南無阿弥陀仏