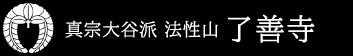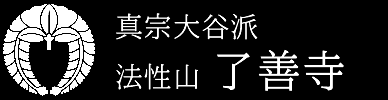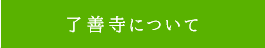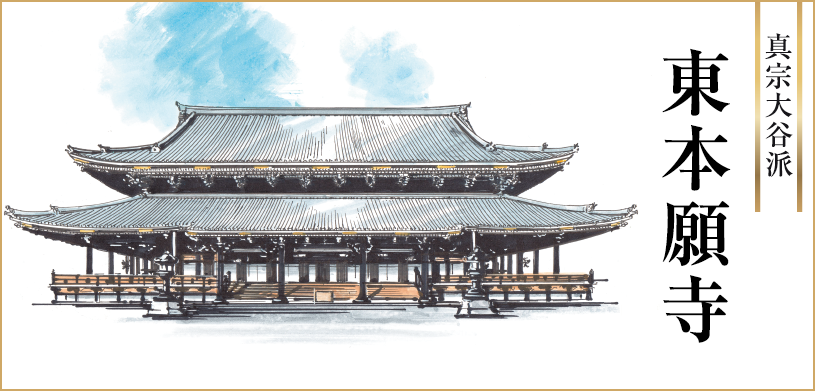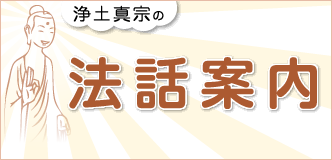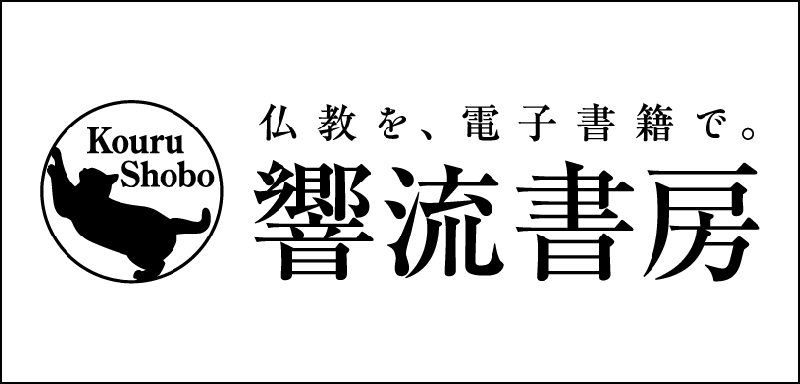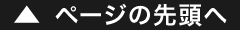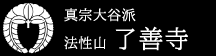道場を開く―9月11日山梨にて
2025.09.30

七夕ではないけれど、毎秋、山梨のブドウ農家K氏宅にて法座が開かれる。Kさんの実母であり、曽我量深師から聞き抜かれた小山貞子さんと親しかった拙寺前住職が薦めたことから、K氏宅にて法座を開くようになったのは2000年頃とも聞いている。
当時、夫の昌美さん(2020年7月1日満81歳にてご西帰・法名:大地院釋覚音)は大の仏法嫌いで、自宅で法座を開くことも渋々了承された。
かつての私と同じである。お互いに聴聞する身となったのだが、寡黙な昌美さんとは「大の仏法嫌い」つながりで、私はどこか通じあっていたように思う。
丹精をこめて黙々とブドウづくりに勤しむ氏は、仏法に生きる人々に対して「世間軽視」の臭みを感じていたのではないかと今にして思う。世間を軽んじて別世界に逃げ込むのは往生浄土の教えではないのだが、往々にしてそういう臭いが抜けきれないのも事実である。大きな陥穽である。

地元山梨はもとより、首都圏、茨城県、滋賀県、石川県からも―
佛念寺藤谷住職 仏道を歩むと見えてくる課題についてレジュメに沿って語られた
今年は、9月11日に法座が開かれた。
真宗宗歌と「総序」拝読の後、昌美さんご西帰後に、手次寺としての縁を結ばれた佛念寺藤谷真行住職、そして私がそれぞれ1席60分の法話。その後にはご家族総出で作ってくださった手製のお斎に舌鼓を打った。山梨名物のほうとうも、採れたばかりのシャインマスカットも、ワインやビールも振舞われ、16時過ぎにお開きとなった。
寺離れ―といわれる中、ここには時間とお金をかけて大勢の方がお参りされ、笑顔で帰っていかれる。何故だろうか。片道5時間かけて、滋賀から日帰りで参詣された方々、体調不良にもかかわらず、石川県からお参りされた方もおられた。
ここは「法座を開きたいから開く人」と「お参りしたいから来る人」しかいないのだから、当然といえば当然の笑顔である。いわゆる組織的動員ではないのである。
国政選挙において、業界団体や労働組合、宗教団体の集票力が大幅に低下した時代状況をよく見なければならない。宗派や寺院も例外でなく、「人目・仁義」(『御俗姓』)、義理や付き合いが行動原理になる時代は終わっている。むしろ中間団体の利益や体面を保つためでしかないことが見抜かれているということだろう。
帰路、中央高速を運転しながら、親鸞聖人が遭遇した吉水の僧伽は、まさにこういう情景ではなかったのか―との思いが湧いた。
大谷派も、本願寺派も、無宗教を標榜する人も、僧分も、みな平坐である。
念仏申し、語りあい、お斎を共にし、1年ぶりの再会を、また初めての出遇いに胸を躍らせ、お土産のブドウを手に、問題の渦巻く暮らしに帰っていく。
とはいえ息抜きや癒しでなく、何らかの気づきや問い返しや発見が身に刻まれているに違いない。古来言われる通り「仏法とつっかえ棒は遠いほど効く」のであるが、それは遠隔地に行くことを推奨しているのでなく、この身を法座に向かわしめる本願力の効能、作用を讃嘆しているのである。
1日限りの法座が生まれるまでには、こちらが気づこうと気づくまいと、無数の諸仏が身を捨てた歴史がきっとある。南無阿弥陀仏