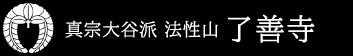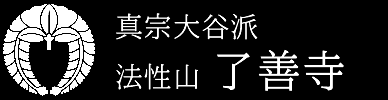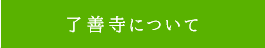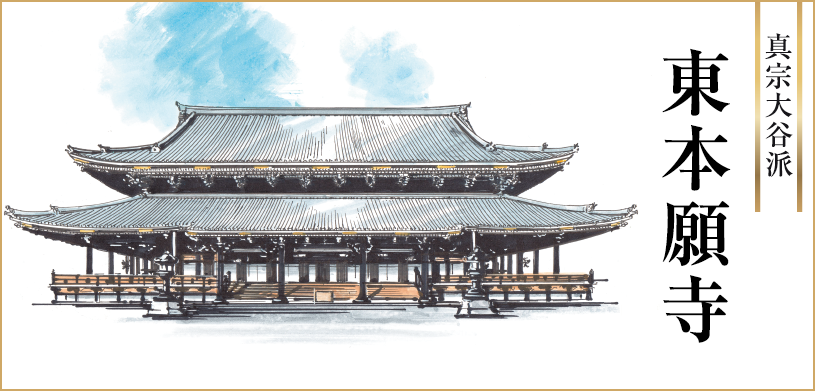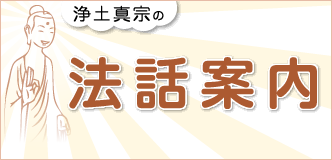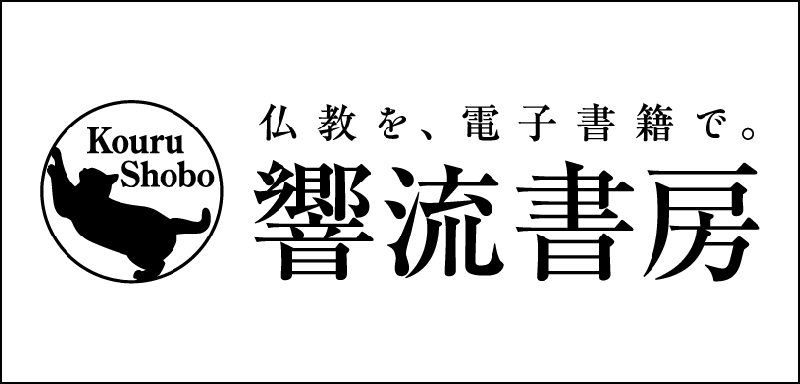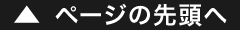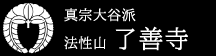【開催報告】7/13(日)盆法要勤まりました
2025.07.13

涼しかった昨日から一転、夏の暑さが戻った7月13日(日)14時~15時半、盆法要が勤まりました。初盆の門徒家族を含め、本堂には41名が参詣、Zoom参詣は11名でした。
普段は法座にお参りしない門徒も「初盆だから」と暑い中をお参りされました。「みずから法を説きて聞かする人ならねども、法を聞かする縁となる人をも善知識と名づく」(存覚上人『浄土真要鈔』・第1版聖典722頁)、(趣意:その方が仏法に通じていなくても、私に聞法の縁を開く導き手をも「諸仏善知識」と名づける)との聖教が事実となって迫ってきました。死という出来事の重さと厳粛さ、そしてそのはたらきを知らされます。

皆で「仏説阿弥陀経」、「弥陀経和讃」等を勤め、その後に約45分の法話、15時30分に法要を終えました。
先月29日にご西帰された池田勇諦先生は「葬儀の時には「やすらかにお眠りください」と言っておきながら、例えば、半年が過ぎて旅行に行く―となったら、お内仏(仏壇)に向かって、チンチンとリンを叩いて「お父さん。留守中頼みますよ」と。眠らせたはずが叩き起こしているんや」と言われていました。
思わず笑ってしまいますが、眠らせたり、ガードマンを頼んだり・・。私たちは無茶苦茶なのです。
真宗に供養がないのではありません。都合によって眠らせたり起こしたりする身勝手さを照らされつつ、「真の供養とは何か」を聴聞する「聞法供養」こそ、真宗の供養でしょう。あの方が私に何を叫んでいるのかを聞き続ける姿勢を賜るところに、人間として最も健全な亡き方との関係が始まるのでしょう。

池田勇諦先生が6月29日にご西帰されて、ちょうど2週間です。私にとっては、『教行信証』後序の「悲喜の涙」との一語が去来しながらの今日の盆法要でした。「悲喜」とは遇いがたくして遇った喜びと今生における別離の悲しみでしょう。
親鸞聖人は法然上人は「化縁すでにつき」た、ご化導を尽くしていかれた―と和讃で詠われています。聞くべきことはみな聞かせていただきました―と親鸞聖人が言いきれたのは、師のご西帰を知った時だったのか、あるいは晩年になってからでしょうか。
2008年に初めて西恩寺様にお参りした際、夕刻のお斎にて、突如「百々海さん。アンタにとって仏法とは何か?」と問われた声が耳の底に鮮明に刻まれています。「アンタ」とは、聖教では「汝」です。
皆さま、ようこそお参りくださいました。今日を出発点として、共に聴聞していきましょう。いずれ聴聞の場での再拝を。南無阿弥陀仏